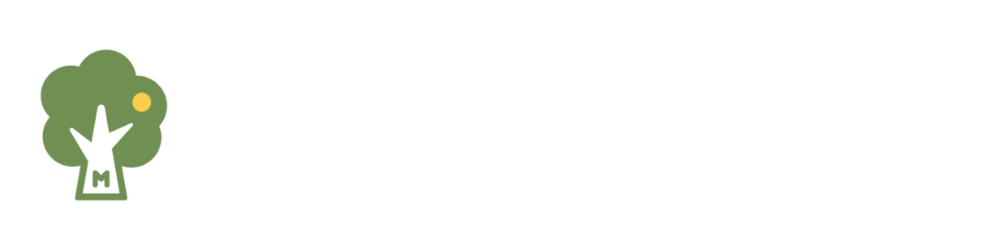相続税の
は、土地の評価額を減額することができる特例です。
適用できるかどうかが、税額や申告要否に大きく影響するため、ご存知の方も多いですよね。

一緒に住んでいたら8割引になるやつですよね?

はい。でも種類が色々あって、ほかのものもあるんです。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地には
のほかに
といったものもあります。
各区分の概要と選択適用について解説します。
対象となる宅地
特定居住用宅地等
被相続人等の、居住用建物の敷地であった宅地等が対象です。
相続した人によって要件が異なりますが、配偶者なら
するだけでOKです。
配偶者以外で、存命中に同居していた親族なら
の3要件です。
別居していた親族に対する、いわゆる
については、さらに要件がたくさんあって厳しくなります。
なんてったって
です。
どうにかして適用しようと、悪いことを企む人もいますよね。
この特例は、相続によって
ようなことがないように、設けられている制度です。
残された家族の生活の安定のためのものですので、趣旨から外れた状況である場合は適用外です。
適用できる限度面積は
です。

広い家だとダメなんですね。

いえいえ。一部について適用できます。
敷地面積が330㎡を超えている場合は、330㎡分まで適用できるという意味です。
特定事業用等宅地等
特定居住用宅地等と同様に
となるのが
です。
2つを合わせて
と呼ぶこともあります。
被相続人等の、事業用建物の敷地であった宅地等が対象です。
要件には、特定事業用宅地等の場合なら、親族が
といったものがあります。
こちらも特定居住用宅地等と同様に、残された家族の生活の安定のために設けられている制度です。
事業により収入を得て、生活を維持するために必要な財産であるため、相続税の負担が軽減されます。
したがって、相続した親族が事業を引き継ぎ、その状態を維持していることが要件となります。
限度面積は
です。
なお、特定事業用等宅地等の「事業」に
は含まれません。
その代わりに、もうひとつ別の区分があります。
貸付事業用宅地等
被相続人等の、貸付事業用建物の敷地であった宅地等が対象です。
特定事業用宅地等と同様に、親族が
といった要件があります。
こちらも他の区分と同様に、残された家族の生活の安定のために設けられている制度です。
貸付事業により収入を得て、生活を維持するために必要な財産であるため、相続税の負担が軽減されます。
したがって、相続した親族が貸付事業を引き継ぎ、その状態を維持していることが要件となります。
限度面積は
減額割合は
です。
各区分のまとめと選択適用
各区分の限度面積と減額割合をまとめると、以下のようになります
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等(特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等)は併用ができて、限度面積は合わせて730㎡になります。
貸付事業用宅地と、特定居住用宅地等または特定事業用等宅地等を併用する場合は、一定の調整計算を行います。
適用できる区分が2以上ある場合は、選択適用となりますが
ことを考えると、原則として、限度面積と減額割合が大きい区分から優先して適用することになります。

8割引の方が絶対に得ですよね。

まれに、そうとは言えないこともあります。
ここで、極端な例をひとつ見てみましょう。
被相続人が、以下のような2つの土地を持っていたとします。

自宅は辺鄙なところなんですが、アパートは便利な場所にあるんです。

たしかに、評価額が大きく異なりますね。

昔は畑だったらしいんですが、都市開発で便利な場所に変わったみたいです。

それでアパート(宅地)に変更したのですね。
そんなわけで、都市近郊の古くからある農村などでは、昔から所有していた近隣の土地の周囲の環境が変わり、自宅と貸アパートの評価額が大きく異なる場合があります。
では、減額金額をそれぞれ計算してみましょう。
いずれも、適用要件は満たしているものとします。
まずは
を選択した場合です。
対象となるのは330㎡分ですから
です。
これの8割引ですから、減額される金額は
になります。
続いて
を選択した場合です。
貸付用の場合は、自分で使っている敷地(自用地)ではなく
といって、地域ごとに定められた、借地権割合と借家権割合を考慮して評価をします。
したがって、仮に
とすると、評価額は
となります。
このうち200㎡分が対象となりますので
となり、5割引の減額金額は
となります。

貸付用の方が減額される金額が大きいですね!

そうですね。
このように、貸付用の方が減額金額が大きくなるのは極端な例ですが、適用できる区分が複数ある場合は、優先順位の判定を行って選択する必要があります。
もちろん
ように選択することが原則ですが、税額だけでなく、遺産分割等の事情もふまえて、ご家族全員にとって最良の選択ができるといいですね。
おわりに
相続税の
の対象となる
について解説しました。
正確に計算をして、最適な選択をしたいですね。
申告要否、簡易シミュレーション、相続対策等のご相談は、個別相談にて承っております。