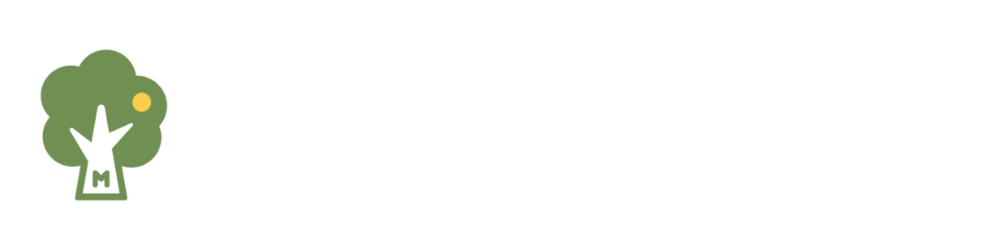取引先から取引先の社名が入った陳列棚を安く譲ってもらいました。
取得価額や減価償却はどうなりますか?

広告宣伝用資産の低価買入ですね。
薬局や喫茶店などでよくあるお話ですね。
法人税では、減価償却資産の取得価額は時価で計算します。
実際の売買金額との間に差額がある場合と、その資産が広告宣伝のためのものである場合の処理を、売る側と買う側の双方の立場でみていきましょう。
一般の資産の場合
例

A社は90万円で購入した陳列棚を、B社に20万円で売りました。
売る側(A社)の処理
| (現金預金)200,000 | (資産)900,000 |
| (寄付金)700,000 |
差額の70万円は寄付金になりますが、寄付金の損金不算入の規定により一部しか損金になりません。
買う側(B社)の処理
| (資産)900,000 | (現金預金)200,000 |
| (受贈益)700,000 |
取得価額を90万円として減価償却の償却限度額の計算をします。
差額の70万円は受贈益(益金)になります。
広告宣伝用資産の概要
社名やロゴマークなどが入った広告宣伝用の資産。
タダでもらったり格安で譲ってもらったりしても、ほんとはまっさらの新品がよかったですよね(笑)
でもそれなりに使えるものもあります。広告宣伝と併用できるものですね。
一方で、どう考えても宣伝のためにしか使えないものもあります。こちらは広告宣伝専用のものです。
このように、広告宣伝用資産には2種類あります。
具体的には以下のような分類になります。
そしてこの専用か併用かによって、一部処理方法が異なります。
詳しくみてみましょう。
広告宣伝用資産(専用)の場合
例

A社は90万円で購入したA社の社名入りの看板を、B社に20万円で売りました。
売る側(A社)の処理
| (現金預金)200,000 | (資産)900,000 |
| (繰延資産)700,000 |
差額の70万円は繰延資産になります。(実際には長期前払費用などの勘定科目で計上することが多いです。)
そしてこの繰延資産の償却限度額は、以下のいずれか短い償却期間で計算します。
買う側(B社)の処理
| (資産)200,000 | (現金預金)200,000 |
取得価額を20万円として減価償却の償却限度額の計算をします。
広告宣伝専用の資産は、ほかの用途にまったく使えませんので、受贈益はないものとして計算します。
広告宣伝用資産(併用)の場合
例

A社は90万円で購入したA社の社名入りの陳列棚を、B社に20万円で売りました。
売る側(A社)の処理
| (現金預金)200,000 | (資産)900,000 |
| (繰延資産)700,000 |
差額の70万円は繰延資産になります。(実際には長期前払費用などの勘定科目で計上することが多いです。)
そしてこの繰延資産の償却限度額は、以下のいずれか短い償却期間で計算します。
売る側については、専用と併用で違いはありません。
買う側(B社)の処理
まず受贈益の額を計算します。
買う側にとっては、まっさらの新品と比べると3分の2ぐらいの価値しかないと考えて
となります。
例の場合なら、90万円×2/3-20万円=40万円ですね。
そしてこの受贈益が30万円を超えているかどうかを判定します。
受贈益が30万円超の場合
| (資産)600,000 | (現金預金)200,000 |
| (受贈益)400,000 |
取得価額を60万円(買う側の負担額+受贈益)として減価償却の償却限度額の計算をします。
少額減価償却資産などの判定は、この計算後の取得価額(買う側の負担額+受贈益)で行います。
受贈益が30万円以下の場合
少額ですので受贈益はないものとして、広告宣伝用資産(専用)と同じ取り扱いになります。
おわりに
広告宣伝用資産の取り扱いについて、売る側と買う側の双方の処理を紹介しました。
薬局、喫茶店、飲食店などの店舗では、取引先のメーカーなどから広告宣伝用の資産をもらうことがありますよね。
計算例は低価買入の場合でしたが、タダ(無料)でもらったときも同じです。
計算方法が特殊ですので頭の片隅にいれておきましょう。