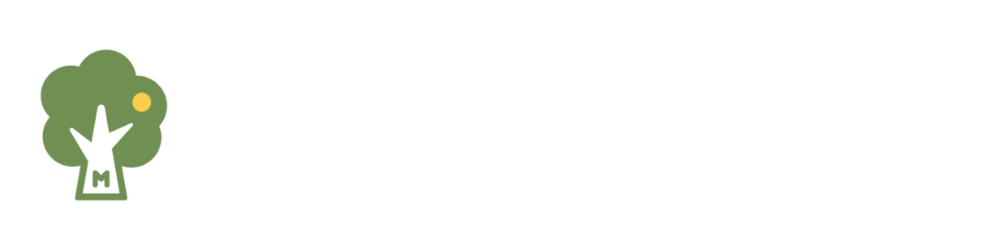2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が始まります。
この軽減税率の対象となる主なものは飲食料品です。

じゃあレストランで食事をしたときも8%?

いえいえ。残念ながら10%なんです。
レストランでの食事は外食に該当し、軽減税率の対象からは除かれています。
軽減税率の対象から除かれる外食。
具体的にどのような状況をいうのでしょうか。
軽減税率の対象となるかどうかの境界線が気になるところですね。
事例とあわせて、詳しくみていきましょう。
外食とは
軽減税率が適用されない外食とは
のことです。
レストランなどでの食事が思い浮かびますね。
飲食店業等の等って気になりませんか?するどいですね。
そうです。いわゆる飲食店だけでなく、すべての飲食サービスが該当します。
ちなみに飲食設備は
なんだか範囲が広そうですね。
これは外食なのにこれは違うの!?というおもしろ事例がたくさんありますのでご紹介します。
カラオケボックスと映画館
カラオケボックスは歌を歌う部屋です。でもテーブルと椅子があって食事もできます。
国税庁によると、カラオケボックスでの飲食料品の提供について
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑵)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂) 問59
という回答があります。
カラオケボックスでの食事は外食なんですね。
客室のテーブルやいすは飲食設備に該当するようです。
注文してもってきてもらうというところがポイントですね。
では映画館はどうでしょうか。
最近は動画の配信サービスが人気ですね。映画館に行く人は減ってしまったのでしょうか。
映画館では、なぜかポップコーンを買ってしまいませんか。もちろん飲み物も。
売店で買って、座席に持っていき、映画を観ながら食べたり飲んだりしますよね。
あの座席(椅子)も飲食設備なのでしょうか。
映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売しているものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問60
どうやら映画館の座席は飲食設備ではないようです。
ただし、食事をしながら映画が観られることを売りにした特別席のような座席だと、外食になります。
2 売店により、例えば、映画館の座席で次のような飲食料品の提供が行われる場合には、当該飲食料品の提供は、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10(注)2)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問60
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
野球場なんかでもありますよね。スタンドの上の方にあるガラス張りの部屋。
食事をしながらスポーツ観戦を楽しめるレストラン。当然外食ですね。
一方、売店や売り子さんから買うのは外食ではありませんので、軽減税率の対象です。
ただし、映画館でも野球場でも、売店前に設置されたテーブルセットなんかで食べると外食です。
ややこしいですね。
ポイントは「飲食料品の譲渡」なのか「食事の提供」なのかです。
単なる販売なのか、飲食サービスなのかってことです。
鉄オタも困惑:食堂車vs車内販売
鉄道。結構好きです。
鉄オタといえるほど詳しくないですが、なにを隠そう、トワイライトエクスプレスの乗車経験があります。
旅行会社で働いたときに、ベテランの男性社員の方にうらやましがられました。
鉄道(旅行)の達人なのに乗ったことがなかったそうで、ド素人のこちらは少し申し訳ない気持ちになりました。
ドイツの鉄道、特にICEはとても快適でしたし、もちろん日本の新幹線(のぞみ、ひかり)も。
鹿児島行きのさくらもお気に入りです。
出雲大社へはスーパーやくも。
北海道ではおおぞら。こちらは電車ではなく汽車なんだそうです。
北海道の友人が電車のことを汽車というので、方言なのかなーと思っていたら、ほんとうに汽車でした。
線路の上に電線ないでしょ?といわれ、アハ体験でした。
東北新幹線や北陸新幹線にも乗ってみたいですね。
観光列車や田舎の一両編成の列車なんかも好きです。
さて前置きが長すぎましたが、列車内の消費税について。
カラオケボックスと映画館の記事をお読みになった方はうすうすお気づきだと思いますが、列車の事例だけを知りたい鉄オタの方に向けて、食堂車と移動ワゴンの事例のご紹介です。
まず食堂車はどうでしょうか。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問58
列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑸)。
食堂車は明らかに飲食サービス(食事の提供)ですね。レストランと同じです。
では移動ワゴンは?
他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します(軽減通達 10(注)2)。
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問58
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の適用対象となります。
移動ワゴンは単なる飲食料品の譲渡です。
ただし、食堂車でなく座席で飲食する場合でも、メニューがおいてあり注文して持ってきてもらったり、食事の予約をしていたりする場合には、飲食サービスになります。
まとめると
となります。
ホテルの客室は飲食設備?
宿泊施設での飲食についても、判断が難しく細かい事例があります。
まずホテルのレストラン。これは当然外食ですよね。
ではルームサービスは?
ホテル等の客室から、ホテル等が直接運営する又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問61
ルームサービスも外食になります。
カラオケボックスと同じような感じですね。
注文して部屋にもってきてもらうという飲食サービス(「食事の提供」)になります。
では部屋の冷蔵庫にあるジュースを、ルームサービスで飲食設備とされた、部屋の椅子に座って飲んだ場合はどうでしょうか。
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問62
こちらは単なる販売(「飲食料品の譲渡」)とされ、軽減税率の対象となります。
同じ椅子でも、飲食設備とされる場合とされない場合があるのはおもしろいですね。
あくまで、どのような過程で飲食に至るかが重要です。
飲食サービス(食事の提供)によるものか、単なる販売(飲食料品の譲渡)によるものかが判断基準です。
屋台の取り扱い。中華街の食べ歩きと博多ラーメン。
続いては屋台の取り扱いです。
こちらは飲食設備にポイントがあります。
屋台のおでん屋やラーメン屋で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問44
ここでいう飲食設備は、飲食のための専用の設備である必要はなく、また、飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているときは、「飲食設備」に該当します(軽減通達9)。
屋台を営んでいるお店の人が
テーブルや椅子を設置していたり、ほかの人が設置して使用許可を受けたテーブルや椅子がある場合には、飲食サービス(食事の提供)となり軽減税率の対象外(外食)となります。
一方、テーブルや椅子がなかったり、近くにあっても使用許可をとっていない場合などには、単なる販売(飲食料品の譲渡)となり軽減税率の対象となります。
以前、博多の屋台が集まっている有名な場所でラーメンを食べたことがあります。
屋台といっても立派な店構えで、椅子とカウンターがあり、お店の人に注文をして目の前に出してもらいます。
この場合は飲食サービス(食事の提供)ですので、軽減税率の対象外(外食)ですね。
一方、外国の友人が神戸に遊びにきたときに、中華街を案内したことがあるのですが、食べ歩きが好評でした。
少しずついろんなものを試せて最高!とのことでした。
食べ物を買って、歩きながら食べ、食べ終わったらまた次の食べ物を買って…
と一度も座らずに歩きまわりました。
こちらはすべて、単なる販売(飲食料品の譲渡)ですので軽減税率の対象ですね。
ただし、お店の人が店舗前などに設置している飲食設備で食べた場合には、軽減税率の対象外(外食)になります。
このように、同じお店の同じ飲食物なのに取り扱いが異なる場合については、こちらをご覧ください。
飲食店の持ち帰り
最後に飲食店の持ち帰りのお話です。

持ち帰りはどんなときも8%でしょ?もうわかったって。

そうなんですけど、ひとつだけ注意しておいていただきたいことがあるんです。
持ち帰りは、単なる販売(飲食料品の譲渡)ですので、軽減税率の対象です。
ただし、こういう場合はどうでしょうか。
飲食店で食事をしたけど、注文しすぎておなかいっぱい。残りを持ち帰りたい。
なにやら雲行きが怪しくなってきましたね。事例をご紹介しましょう。
お寿司屋さんで、パック詰めしたお寿司を持ち帰る場合の事例です。
店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
なお、顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにして販売するものは、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問52
いったん飲食サービス(食事の提供)として注文してしまったものは、あとから持ち帰ると言っても、単なる販売(飲食料品の譲渡)には変わりません。
つまり、食べ残しを持ち帰りたい場合の持ち帰り分も、軽減税率の対象外(外食)のままとなります。
この事例のポイントは「いつ」ですね。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則 34①一イ、軽減通達 11)。
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)問52
単なる販売なのか飲食サービスなのかが決まるのは、販売(または提供)時点です。
飲食店での注文は食べきれる範囲で、また、持ち帰って家でも食べたい場合には、注文する時に別途持ち帰り用として頼んでおきましょう。
持ち帰りの意思確認などについてはこちらをご覧ください。
まとめ
軽減税率の対象から除かれている外食についてお話ししてきました。
同じものを食べても、一方は8%で、もう一方は10%。
同じ場所で食べても、一方は8%で、もう一方は10%。
興味深い事例をいくつかご紹介しましたが、しばらくは混乱しそうですね。
ポイントは
持ち帰るつもりのときは、くれぐれも、うっかり「ここで食べます」なんて言ってしまわないようにしましょう。