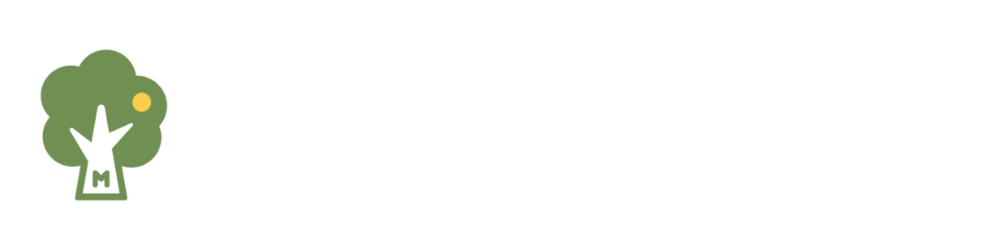つい最近、年配の方の文章を読む機会があり、難読漢字や知らなかった言葉がたくさん出てきました。
子どもの頃に習字に通っていたので、漢字はどちらかというと得意な方です。(多分…。)
最近の小説なら、漢字が読めないことはほとんどありません。
でも、江戸川乱歩や、アガサクリスティーの古い翻訳などになると

漢字が難しすぎる…。
と、読めないこともたまにあります。
そんな江戸川乱歩的な気分(?)を味わった出来事でした。
その中で、特に興味深かった言葉とともに
をご紹介します。
難しい言葉
まず話題にのぼったのが
です。
「勧める」という意味で、類語としては「勧奨」や「推奨」が近いです。
業界的には
が頻出例文(?)ですが、今は税務署でも使っていないそうです。
ちなみに、JR(国鉄)でも昔は使っていたようで、ちょうど昨夏に、駅の掲示板に書かれていたとかで話題になっていたようです。
省庁や公正取引委員会では、インボイス制度に関する内容で
という文言で使われています。
難読漢字
初めて知った漢字で面白かったのが
です。
ギュウギュウ詰めのたくさんの牛が、パッと頭に浮かび、一瞬で覚えることができました。

覚え方は「牛がひしめく」だね。
ちなみに、同じ漢字を組み合わせて作られる漢字は結構たくさんあって
とかは有名ですよね。
画数が多いのだと、龍が4つで

「てつ」と読むそうです。(私のパソコンでは出ませんでした。)
画数は64画で、「言葉が多い」という意味です。

たしかに色々多いね。
読みと意味が同じ漢字(異体字)
見たことがないような漢字でも、文脈で読めるときがあります。
の「嘗める」は、単独だと読めなかったかもしれません。
「舐める」の方が一般的ですよね。
読み方も意味も同じで、どちら(どれ)を使ってもよいということは、よくあります。
また、「嘗める」のほかに「甞める」もあります。
このような、少しだけ形が違うものを異体字と言います。
人名に多く、代表的なのは
でしょうか。
渡辺さんの「辺」は、なんと30種類以上の異体字があるそうです。
私のパソコンでは
しか出ませんでしたが、「自」ではなく「白」だったり、しんにょうの点はひとつだったり、ちょっとした違いの異体字がたくさんあります。
の「斉」も難しい異体字がありますよね。
ちなみに

「斉」は簡単なやつなんですが、「とう」は「東」です。
というパターンもあるのでご注意下さい。(笑)
そのほか
などはよく目にしますよね。
最近知ったのは
です。
は知っていましたが

もうひとつあるの!?
と、必死でキーボードのスペースキー(漢字変換)を押しました。(笑)
ひらがなとカタカナと漢字(翻訳語)
ひらがなの方が見慣れているものも、漢字を使われている箇所がたくさんありました。
などです。

最近はなんでもすぐにひらがなで書くのぅ…。
それどころか、カタカナの外来語ばかりじゃ。

そうですね。
でも、外来語はカタカナのものだけじゃないですよ。
中国からは、文字と一緒に、それまで日本になかった言葉もたくさん入ってきています。
日本に元々あった言葉は「和語」、中国から入ってきた言葉は「漢語」です。
などは漢語です。
さらに、日本で独自に作られた漢語は「和製漢語」とよばれ、逆輸入もされています。
などは、中国で使われるようになった和製漢語です。

中国はもともと漢字があるじゃろ。
漢字のない国の言葉のことを言っとるのじゃよ。

はい。漢字がない国の言葉も、はじめは漢字で日本語にしていたんです。

なぬー!
外国の言葉を日本語に翻訳した単語のことを、翻訳語といいます。
などは、翻訳語です。
ちなみに、「society」から「社会」という翻訳語を作ったのは福沢諭吉だそうで、彼はたくさんの翻訳語を作ったそうです。(「彼」も翻訳語です。)
ところが、外国の言葉がどんどん入ってくるので、翻訳語を作るのが間に合わなくなり、カタカナで書くように変わっていったそうです。
ちなみに
は漢字ですが、ポルトガル語(confeito)です。
ポルトガル語やオランダ語は、江戸時代から入ってきているので、日本語になっているものが多いです。
また、医学用語などはドイツ語、料理関係ならフランス語、音楽用語はイタリア語が多いようですね。
おまけ
文末の締めとして
とありました。

「むかしび」って何ですか?
と聞いたら、複数人から一斉に「せきじつ!」と突っ込まれました。
難読でも何でもなく、知らなかっただけでした。(笑)
おわりに
年配の方の文章を読んで、初めて知った言葉や漢字と
を紹介しました。
難しい言葉の使用頻度、難易度の推測、ひらがな・カタカナ・漢字のバランスなどは、文章を書くときの悩みの種です。
日本語は、難しい言葉はもちろん、漢字が多すぎると難解になりますが、だからと言って、ひらがなだけで書くと猛烈に読みにくくなるという不思議な言語です。
内容や読む人、そして時代に合わせて、柔軟に変えていけるといいですね。